
2024年7月22日、東海道新幹線が豊橋と三河安城間で保守車両の衝突・脱線で名古屋=浜松間で終日、運休したことについて考察してみました。
2024年7月22日
2024年7月22日は2011年3月11日とも、1985年8月12日とも違う日でした。数字の並び的には近い気もしますが、この日は結構大きな日でした。
この日は東海道新幹線において、豊橋と三河安城間で保守車両の衝突・脱線が発生し、新幹線が営業する運転する朝6時までに収拾が出来なく、結局は浜松と名古屋間で東海道新幹線は終日運休となり、実質的には東名阪の通常の輸送体系が丸一日崩れた日でもあります。
区間運休的には短いのでありますが、時間的には東京と名古屋・新大阪間が丸一日k、乗り換えなしで移動できなくなったのは新幹線開業以来の出来事といっても過言ではありません。
バックアッププランはなかったのか
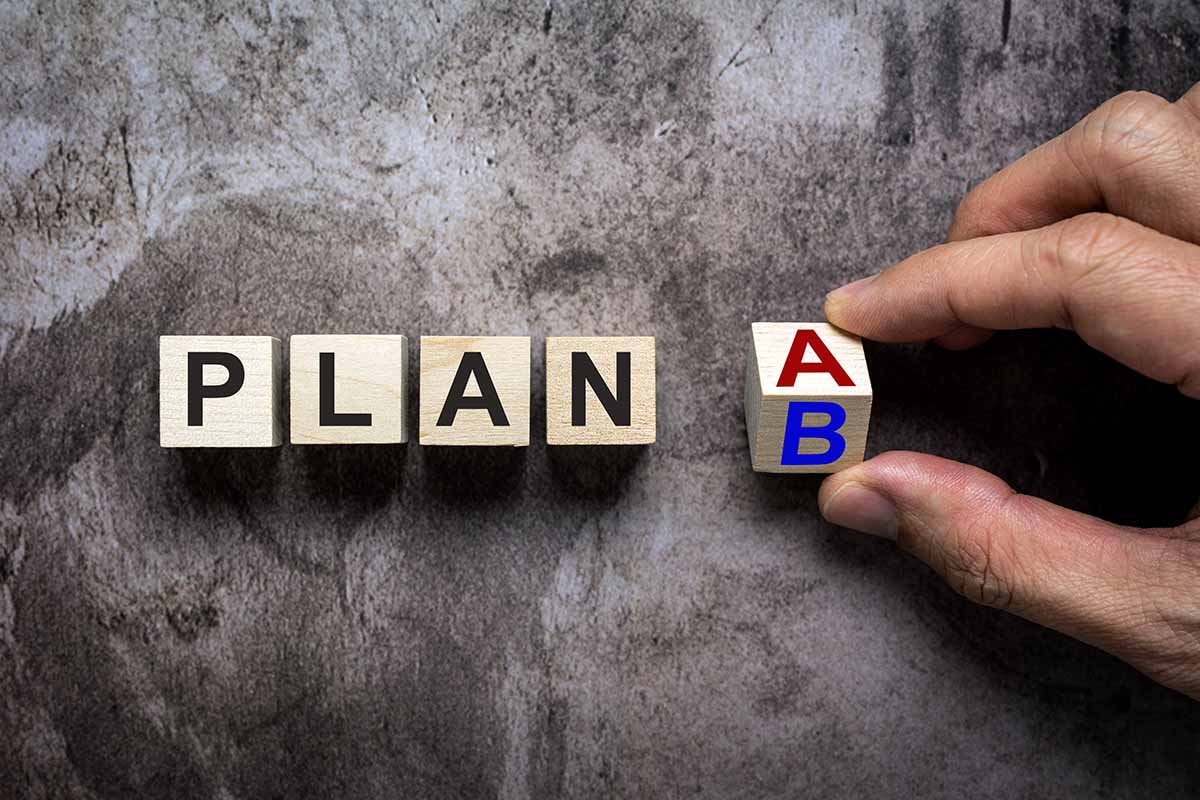
東日本大震災を含めて、その余震などで被害を受けて数か月から数週間不通になっている東北新幹線では、そうした不通が起きると在来線の東北本線に特急車両利用の快速を運行したり、かつては東北本線よりも所要が早かった、常磐線経由で特急車両の快速をすぐに運行しており、東名阪に大動脈を握るJR東海がそうしたバックアッププランがなかったのかと感じてしまいます。
今回のトラブルで在来線の東海道本線やアルプスを北に迂回する中央本線は影響を受けていないわけであり、東北新幹線のように在来線の東北本線に臨時便を出したり、中央本線にしなのとあずさを増発すると言う事も考えられたと言えます。
さらに言うと、2024年3月に延伸した北陸新幹線に迂回を求めても良いところでしたが、それはなく、JR東海公式では、「駅に来ないでください」となっていました。
不適切にもほどがあるとも言えますが、しかし、これが事実であるといえます。東海道新幹線の輸送力はすべて16編成でピーク時は3分に1本ぐらい運行されており、1日の輸送力は32万人であり、飛行機と比較すると16倍に達するところであります。
ベルトコンベアで東名阪に人を運んでいるに等しいとも言えます。
これを在来線や北陸新幹線に振り替えても、JR東海は在来線車両を匹敵する車両を保有しておらず、北陸新幹線においても12両編成で東海道新幹線よりも少なく、敦賀から乗り換えるサンダーバート・しらさぎにおいても。さらに輸送力先細る結果と言え、全くの代替は効かないとなります。
飛行機で代替するとなると枠の多い成田空港から頻繁に飛ばせそうですが、そもそも飛行機が足りないと言う事となり、機材とパイロットをレンタルしてくる必要もあります。
そういう意味では、バックアッププランの無いままに輸送力を拡大してきたと言えます。これは100%悪いといは言えず、平時では東名阪間を航空よりも高速道路よりも大量の民間人の移動を支えており、それを最短3分間隔まで詰めてきたことは偉業とも言えます。
ただ、有事の際にはそのバックアッププランがないので、大雨や今回のような事例では時間が長引くと経済成長にも影響が出てきます。
以上のように、今回の顛末を見ても、東海道新幹線は正常に動いていれば世界一のベルトコンベアであり、東名阪間で大量の人間を移動できますが、それが一度、トラブルが出るとそのバックアップがないと言えます。
仮に、リニアが出来てもそれが解消はできず、地震がないことを祈りつつ、毎日を過ごすこととなりそうです。ただ、東南海地震で津波が来れば弁天島辺りは確実に年単位で復旧はできなく、結構影響はあると思います。
まあ、神奈川・最西端で難工事で未だに全通していない新東名が開通してから大きな地震が来て欲しいところでもあります。それ以前に起きたら、車やトラックの需要が増えて、自動車産業は繁盛するかもしれませんが、工場が東南海にあると操業自体の問題も出てきます。。
輸送体系2.0が完了は2040年

20204年の輸送体系を妄想してみました、高速道路は新東名・新名神の全通が完了し、整備新幹線では札幌までの北海道新幹線が札幌まで開通、空港では成田空港の発着回数が大幅にアップしています。
リニアは名古屋まで開通しており。その先は奈良県内でグダグダして決まっていません。2024年に敦賀乗り換えが発生した時と同じように名古屋で乗り換えが不便な自体となり、安い新幹線を利用する人は多くいます。
輸送体系がようやくアップグレードし、羽田⇔新千歳便は新幹線開通の影響が徐々に出ており、その分を相変わらず利用の多い、羽田⇔大阪伊丹にシフトしています。
北陸新幹線については小浜ルートが費用が掛かり過ぎが2024年に発覚して、新快速が結局が多いので敦賀止まりのままになっています。
西九州新幹線はすべてフル規格で佐賀駅を通り、在来線もそのままとなっています。長崎と関西の往来が格段に便利になっています。
最後に

日本の人口は江戸時代末期には3,300万人であり、そこから一気に第二次大戦まで7,200万人さらに戦後には1.2億人となっており、驚異的とも言えます。
人口の減少が問題と言われていますが、驚異的な増え方をした反動がゆっくりと来ているのかもしれません。人口問題とインフラはいつも一緒に考えられます。人口が減っているので、インフラに回すお金があったら、高齢者福祉を拡充する意見もありますが、高齢者が充実した福祉で若さを取り戻して働いて経済を回せばいいですが、そう簡単ではないでしょう。
インフラ整備は未来につながることであり、将来につながることであり、単に事業費回収だけではないとも言えます。もっと未来をデザインしてインフラ整備に対する熱量があると進められるのかもしれません。
7.22はそうしたことを試された健康診断だったかもしれません。日本の脆弱性を示した事例であり、これが数年単位で続いたら、どうなるかと言うのを実感した日でもありました。